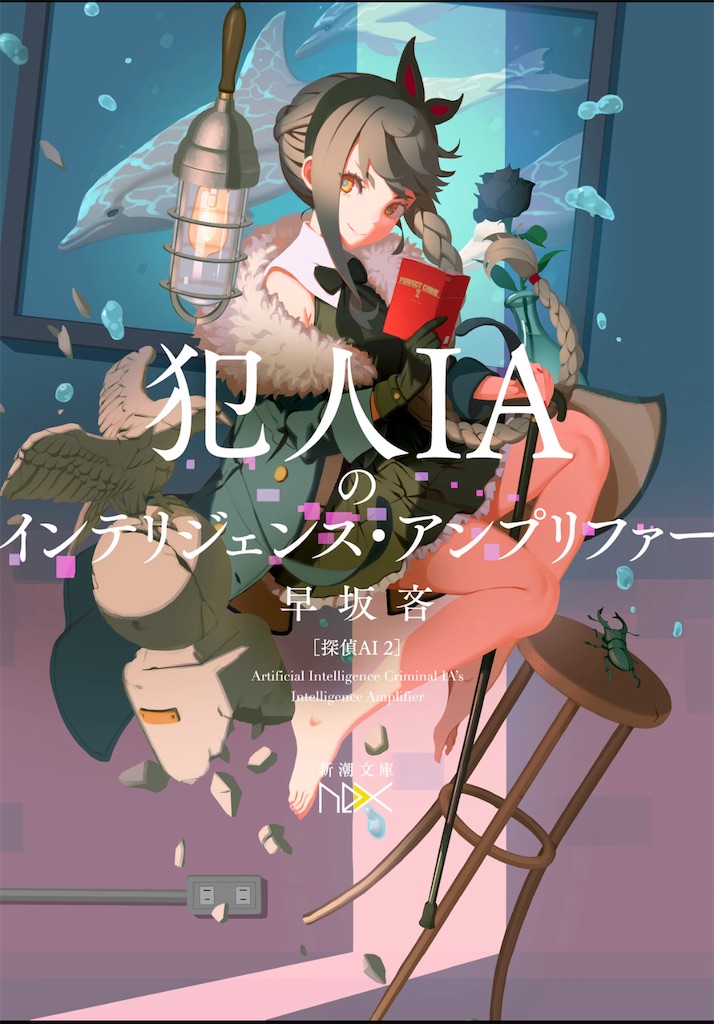・令和元年の人生ゲーム
著者:麻布競馬場
出版:文藝春秋(Kindle版)

都知事選に出馬した安野貴博さんのパートナーは文藝春秋の編集者らしいです。
応援演説がバリ上手で評判になった彼女が編集した作品のひとつがコレだとか。
https://www.youtube.com/live/-HcHYKuQElo?si=Ku9jwkoOKVLoj0e6(https://www.youtube.com/live/-HcHYKuQElo?si=Ku9jwkoOKVLoj0e6)
前作(この部屋から東京タワーは永遠に見えない)もチョット気になってたので、ちょうどいい機会かなぁと思って読んでみることにしました。
読み終わるまで、直木賞の候補作になってる事は全然知りませんでしたけどw。
\<概要:Amazonより>
「まだ人生に、本気になってるんですか?」
この新人、平成の落ちこぼれか、令和の革命家か――。
「クビにならない最低限の仕事をして、毎日定時で上がって、そうですね、皇居ランでもしたいと思ってます」
慶應の意識高いビジコンサークルで、
働き方改革中のキラキラメガベンチャーで、
「正義」に満ちたZ世代シェアハウスで、
クラフトビールが売りのコミュニティ型銭湯で……
”意識の高い”若者たちのなかにいて、ひとり「何もしない」沼田くん。
彼はなぜ、22歳にして窓際族を決め込んでいるのか?
2021年にTwitterに小説の投稿を始めて以降、瞬く間に「タワマン文学」旋風を巻き起こした麻布競馬場。
デビュー作『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』のスマッシュヒットを受けて、
麻布競馬場が第2作のテーマに選んだものは「Z世代の働き方」。
新社会人になるころには自分の可能性を知りすぎてしまった令和日本の「賢すぎる」若者たち。
そんな「Z世代のリアル」を、麻布競馬場は驚異の解像度で詳らかに。
20代からは「共感しすぎて悶絶した」の声があがる一方で、
部下への接し方に持ち悩みの尽きない方々からは「最強のZ世代の取扱説明書だ!」とも。
「あまりにリアル! あまりに面白い!」と、熱狂者続出中の問題作。
この概要だと「沼田」が主人公になっちゃいますけど、小説としては「意識高い系の学生」と「むちゃくちゃ能力は高いけれども、なぜか覚めてしまっている沼田」を対比して、その両者の間で自分自身のあり方を模索する「語り手」を配する構成となっています。
小説が登場人物の何らかの変化を描くとするなら、本書で変化するポジションにあるのはのはこの「語り手」なんですよね。
平成28年から令和5年までを4つの短編で括り出して(平成28年、平成31年、令和4年、令和5年)、表層的な意識高い系Z世代を冷笑する様な「沼田」の変遷が描かれていますが、その沼田自身がZ世代(最終編で28歳くらい)でもあります。
じゃあ描かれてるという「Z世代の働き方」「Z世代のリアル」って沼田のこと?
それとも浅薄に走り回る意識高い系の学生たち?
「沼田」だと、<能力はあるけど、自己肯定感が低くて、自分の意思で決定できない>ってキャラになるんだけど、Z世代ってそんな感じかなぁ。
あんまりそんな気もしないけど…。
まぁ、そんなこと言うと、そもそも「意識高い系」の若者っていうのが、あんまりピンとこないっていうのがあるんですけどね(自分の子どもたちを見ててもw)。
と、まぁいろいろ思うところはあったりもするんですが、小説してはかなり面白く読むことができました。
「沼田」目線だと、
学生時代に自己肯定感をへし折られた男が紆余曲折の末、自分の「居場所」を見つける。
…みたいな話なんですが、その屈折度合いと空虚さがなかなか興味深い。
ある種の\<時代\>を表していると言うのは確かかもしれないなぁ。
個人的には3作目の「シロクマ騒動」がむちゃくちゃ面白くて、そっちの方向で展開していったら、もっと面白かったのにとは思いましたけどね。
まぁそうなると万城目学さんや森見登美彦さんみたいになっちゃう?
京都からじゃなくて、東京からそういう雰囲気の物語を繰り出しても、それはそれで面白いんじゃないかなぁ…と。
まぁ、余計なお世話ですがw。
前作を遡って読むか
については「留保」。
audibleとかになったら聴くかなw。
ただチョット楽しみな作家さんではありますかね。
ペンネームは何やねん、やけど。